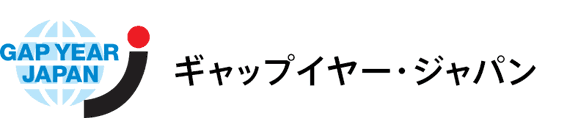「映画を通して未来のカンボジアを創る!~だから今、休学して1年のギャップイヤー」
(写真:カンボジア人スタッフとの写真。左からトゥクトゥクドライバーのパパ、山下、元映写技師のサロン、教来石代表)
山下龍彦(大学生、NPO法人CATiC副代表)
プロ野球選手を目指し高校野球の名門校に入学するも、たったの2ヶ月で中退。
行くあてもなく辿り着いた通信制高校を卒業。その後、一浪で私立文系大学入学。
現在、カンボジアに駐在し現地スタッフと国際協力活動を展開中です。
今、僕は2015年9月から大学3年生を1年間休学し、カンボジアのバッタンバン州という町にNPO法人の駐在員として駐在しています。バッタンバンという町はまだ観光地化しておらず、数年前まで地雷が多く残っていた地域です。この町を拠点にし、カンボジア人と一緒に学校や村を即席の映画館に変えるという活動をしています。
<子どもたちが自由な想像力を生かして創る世界を見たい>
現在副代表を務めるWorld Theater Project(NPO法人CATiC)は、設立から3年が経ちました。僕が駐在するまでは、日本在住の日本人メンバーが長期休みを使ってカンボジアに年に数度渡航し、年に数回カンボジアの学校に赴き上映をするだけでした。
カンボジアという国は、東南アジアの中でも後発国です。確かに近年カンボジアも、他の新興国と同じく経済発展を進めています。しかし現状は、一部の都市の近代化とは正反対に、都市部から車で1時間半も走れば、のどかな田園風景、集落の大半は未だに高床式住居、未だに十分に電気は通っていません。そのような情報に触れる機会の少ない農村部の子どもたちにとって、将来を描くとなると自分の周りの大人しかなく、選択肢が限りなく少ないのが現状です。
この現状は、農村部に住む子どもたちには変えられない環境です。
でも、僕らが映画を通して子どもたちの可能性・世界を広げられたら。子どもたちが生きるこれからの時間、大人になった時の選択肢は、必ず違ったものになると考えます。
この思いは、自分が高校を中退し生きる目的を失っている時に、一本の映画に出会った経験から人生が大きく動いた経験からでした。プロ野球選手を目指し、高校に入るも挫折の末中退をし、俗に言う「引きこもり」の生活をしている時に偶然出会った、「ホテル・ルワンダ」という映画。この作品が、僕が世界を知ること、国際協力という分野に興味を持つきっかけになり、結果として大学に入り、今こうしてカンボジアで駐在する原体験になりました。
映画は、見る人それぞれが自由な感性で作者の思いや世界を感じることができる。そして、そこには自分と重なる世界もあれば、僕が「ホテル・ルワンダ」を見て視野が広がったように自分の知らない世界が描かれているときもある。どちらを取っても、この映画を通した原体験は将来どこかで生きるものだと思います。
しかし、カンボジアの農村部の電化率の低い地域に住む子どもたちは、こうした映画を通した原体験をする機会が圧倒的に少ないのが現状です。だからこそ、僕らがクメール語に吹き替えた日本の質の高い作品を上映し、少しでも多くの子どもたちに映画を通した原体験を届けたい。そして、彼らの創るカンボジアの将来を見てみたい。
そのためには、草の根でどれだけ多くの未知の可能性を持つカンボジアの子どもたちに、映画を届けられるかが鍵になる、そう確信しました。
ただ、自分が1年間の休学を終えたら活動が終わってしまう一過性の活動では意味がない。自分がいなくなった後も、何年も何十年も継続して映画を子どもたちに届けられる形を作りたい。
その時思い出したのは、東北でボランティアをしていた時の経験でした。ボランティアの活動は、初期は外部の人が中心でいい。しかし、持続性を持たせるためには最終的にはしっかりと現地の人が中心として活動をまわせるようにならければならない。現に、震災から3年経った時期から外部からのボランティア団体や活動は減少の一途をたどり、今現在、残る団体の多くは現地の人が中心となって活動しているものです。
この東北の経験から映画を子どもたちに届ける僕らの活動も、何十年と続く活動にするためにはカンボジア人と一緒に活動することが最重要であり、彼らと現地に合う最善の形を模索しながら、作り上げることで持続可能な形にしようと考えました。

<カンボジアだからという考えは、間違いだった>
この活動を持続可能な形にするため、一年大学を休学し、カンボジア人スタッフの育成を行っている中で、現地の人と一緒にやることで見えてくる世界の流れや異国間での仕事の中での大切な事、そしてカンボジアという国をより深く感じることができています。
僕は今、バッタンバンという町で元映写技師で現在郵便配達員、東南アジアでよく見られるトゥクトゥクという乗り物のドライバーの家族と一緒に活動しています。彼らは、カンボジア国内では決して裕福な層ではないだけでなく、例えば郵便配達員、トゥクトゥクのドライバーといった社会的に地位の低い仕事に従事しています。このことは、彼らもよく理解していて、富裕層とそうでない人では生活の水準だけでなく観察したところ、生活様式も大きく異なる気がしています。
そんな僕らのスタッフですが、子どもたちに映画を届けるこの活動を一緒にやるようになって、早4ヶ月で目に見えて顔つきが変わってきました。この変化の理由は、仕事以上に子どもたちのために自分たちが貢献できている。社会との関わり方が自明になり、自分がその一端を担うことができているという自負からきていると思っています。
実際に、始めた当初から比べて打ち合わせの中で彼らが発する意見の中に映画を見る子どもたちの視点が加わるようになり、活動に必要なことを自分なりに考えて、実際に挑戦する動きが生まれてきています。有意義な打ち合わせ、質の高い活動を行うために必要なことは信頼関係とどれだけこちらが根気強く活動の意義、想いを伝えられるかだと思います。諦めずに伝えれば、時間はかかるけど僕のスタッフと同じように彼らも理解し、期待に応えてくれる時が訪れるはずです。
僕は、カンボジアに来る前に大きな間違いをしていたことに、この変化が気づかせてくれました。新興国のカンボジア人だから、このレベルまでしかできないんじゃないか。まだまだ、信頼関係を作っても裏切られることが多いだろう。これは、大きな間違いで確かに先進国の僕らより多くのものには触れてはいないかもしれない。僕らよりも勉強をした時間、経験をした数は少ないかもしれない。
しかし、カンボジア人は彼らなりに人生の中で多くを経験し、そこから学んでいて、ゼロから何かを生み出す時、先進国のアイディアと新興国の人々の持つその場の課題を解決する力を組み合わせると、自分では想像もできない化学反応が起きることがある。そして、何かを一緒にやるとき、異国間も新興国とかそういうレッテルは関係なくて、多少文化の違いもあるけれど、同じ人間であることを念頭に置いて自分の持つ偏見を取っ払うことで自らの幅を広げることができる。この幅が活動が支援する側の一方的なものではなく、される側を巻き込み最適化する重要な要素だと考えています。
僕らのような、社会貢献活動を異国の地でやるときにその地の人とともに活動の最大化をすることが、社会との接点が希薄な人と社会をつなげるきっかけ、活動の可能性を広げる可能性を秘めていると思います。
僕らの活動は、会社と違い事業の成功・失敗が正直わかりにくい活動です。そして、非営利組織の活動は多くの支援をしてくださる人や他の法人によって成り立っている活動です。応援してくださる方々の思いに応えるにはどうしたらいいか、そして成果がわかりにくい中でどのように団体内部のメンバーのモチベーションを高められるか。この問いへの、僕の答えは数字と結果にこだわり、さらにその過程のストーリーも大切にするということでした。
幸い映画を子どもたちに届けるこの活動には、何人の子どもたちに映画を届けられたか、何箇所でできたのか。といった目標値を立てやすい指標があり、この目標値が活動が成功しているのか否かの一つの指標となっています。この目標値は、僕が現地で悩み動けなくなったときに、いかにしてこの目標を達成するかをシンプルに考えられる環境を作ってくれて、僕が道を見失なわないように、数字がある意味で道標のようになってくれています。
正直、23歳で未熟者な自分にとって、活動への期待を背負って単身で、現地に乗り込み、現地スタッフを見つけ育成し完成させるまでを担うのは大きなプレッシャーでした。自分の今の行動が常に、映画を届けるということにつながっているのかを問い続け、何度もプレッシャーに潰されそうになりは、この数字という道標を再確認し、一度落ち着いてから計画を練り直したり、時には現地で活躍する日本人の先輩に相談したりしています。
数字と結果にこだわることで、支援してくれている方や団体のメンバーに対して、それぞれの想いや活動がしっかり現地で還元されていることを伝えられると同時に、自分自身の活動の道標に数字と結果がなってくれています。
昨年、100人にしか映画を届けられなかった僕らですが、今年度、5000人以上の子どもたちに映画を届けることが可能になりました。
そして、この成果は短期的なものではなく現地人スタッフの成長とともに量および質が向上してく数値だと思っています。
非営利活動というとどうしても、数字や結果のようなビジネス的な視点を見落としがちですが、僕は、非営利活動だからこそ数字と結果にこだわることで、活動の意義を高められると考えています。
<1年間のギャップイヤーでの目標>
自分のギャップイヤーも半年が経とうとしています。今、休学を決めたこの決断を後悔していません。大学生のうちに、自分の足を運んで、五感で感じて実際に自分で挑戦や失敗、成功を経験できたことに大きな意義を感じているからです。
僕が休学前に立てた目標は、現在の活動拠点である、バッタンバン。世界遺産アンコールワットのある、シェムリアップ。そして首都、プノンペン。この三箇所で、カンボジア人のスタッフが毎月定期的に映画を子どもたちに届けられるようにすることです。
現地スタッフの育成や活動の中心を現地に置くことの難しさは歴史が示していて、かなり背伸びをした目標でした。しかし、この目標の実現可能性を高めたのはAI(After Internet)という時代でした。
カンボジアも他の新興国とな同じように、都市部に住む人々は格安スマホを持つようになりFacebookが連絡、情報収取のキーデバイスとして働いています。格安スマホとFacebookは、現地スタッフとのコミュニケーションコストを格段に抑えるだけではなく、活動の報告もFacebookでできるため、現地スタッフの管理を数十年前より格段に容易にしています。
結果として、上映の際に自分がいなくてもカンボジア人だけでの上映、報告が可能になり、実際に今では新規拠点の開拓のために上映に参加できないときでも、スタッフの管理を行うことを可能にしています。しかしながら、信頼関係をより強固にするためには、対面で同じ釜のご飯を食べることが大切です。そのバランスを大切にしながら、1年間の目標である3拠点での安定稼働をなんとか達成したいものです。

(写真:リエンポン小学校での野外上映。この日は100人を超える老若男女の村人が集まった)
プロジェクトページ
カンボジアに映画を届けよう〜無鉄砲な大学生の挑戦〜
http://www.catic-fryingpan.com/
プロフィール:
「カンボジアに映画館をつくろう!プロジェクト」
特定非営利活動法人CATiC(Create A Theater in Cambodia)
副代表 山下 龍彦
Twitter:@5296tatsu / https://twitter.com/5296tatsu
FB :山下龍彦 / https://www.facebook.com/tatsuhiko.yamashita.9